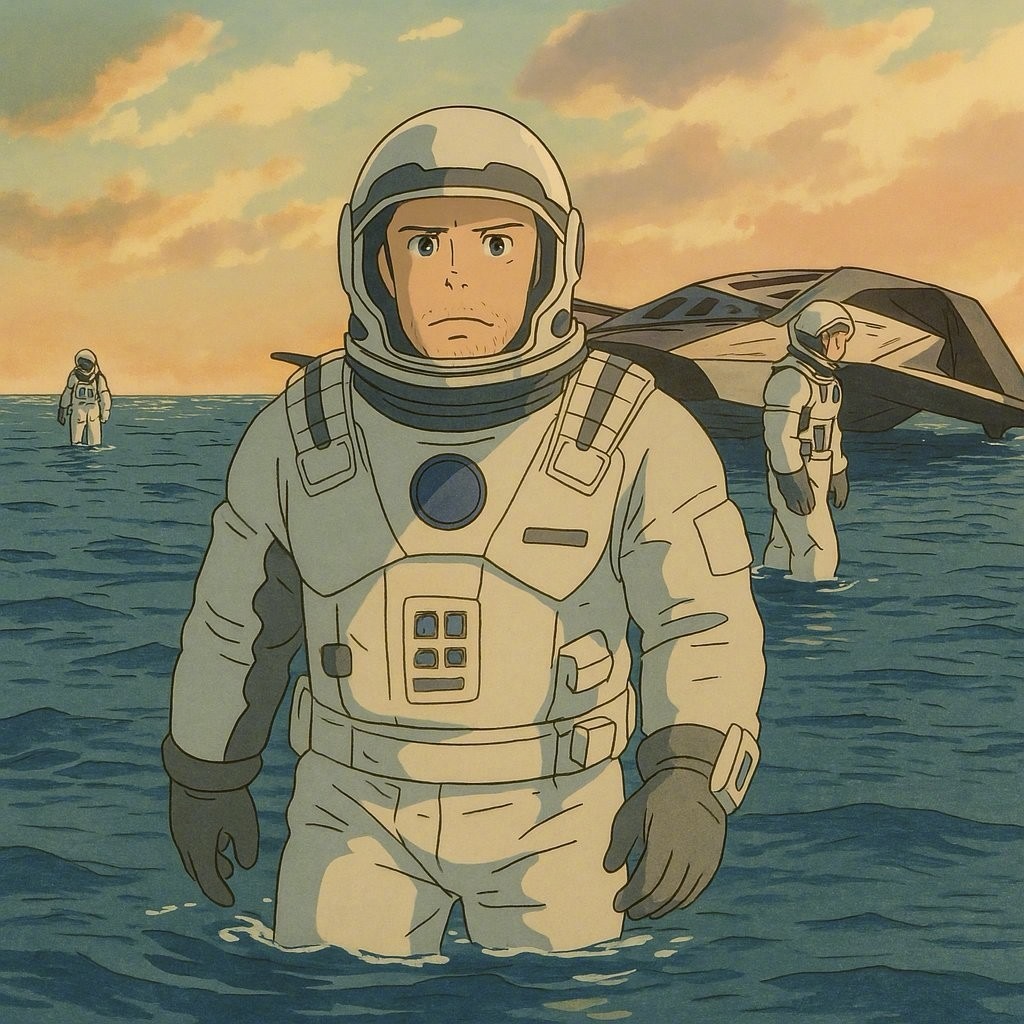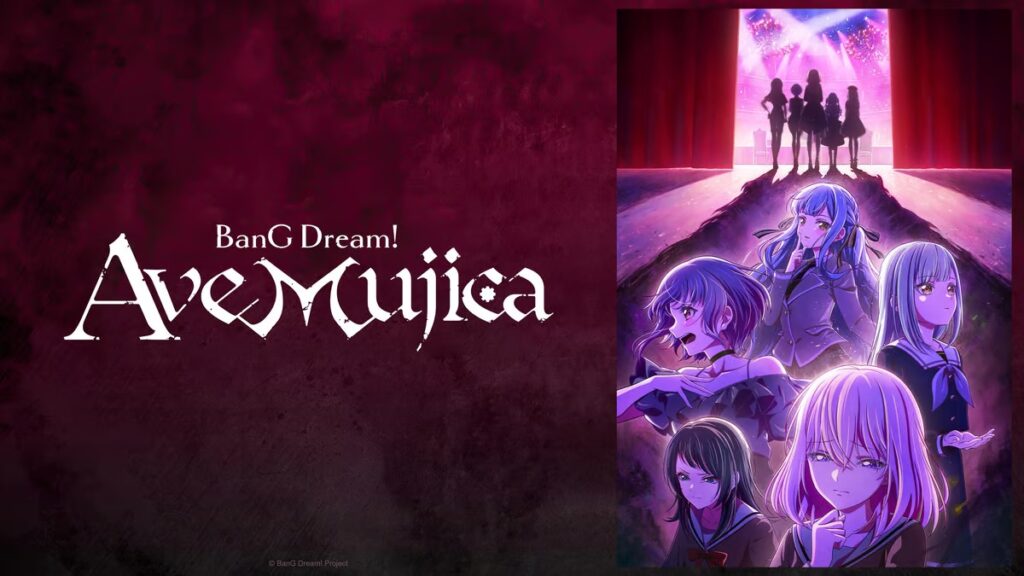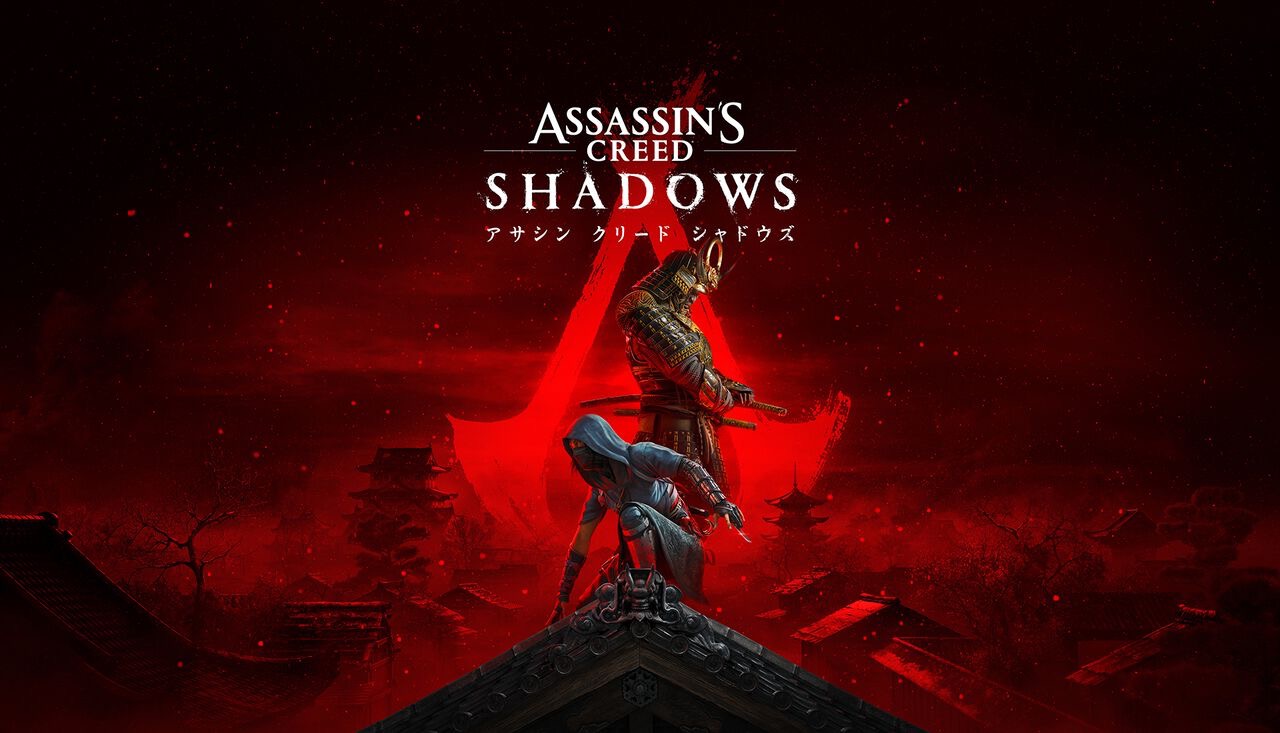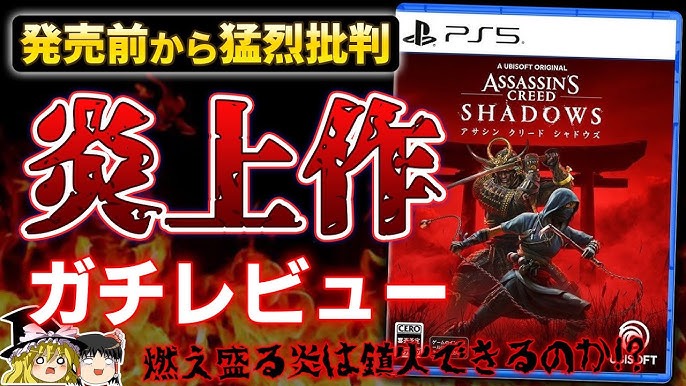【序章】「アサシンクリード」シリーズ最大の炎上
2025年3月20日、ユービーアイソフト(Ubisoft)の最新作『アサシンクリード シャドウズ』が全世界で発売された。日本戦国時代を舞台にした本作は、史料に曖昧な記録しか残されていないアフリカ人武士「弥助」を主人公とする設定で注目を集めたが、発売前から「歴史の歪曲」との批判が噴出した。change.org上での発売中止を求める署名は15万人を突破し、石破茂首相は参院予算委員会で「神社への落書きは国家への侮辱であり、文化的冒涜である」と公式に非難するに至った。さらに、ゲーム内で弥助が皇族の祖墳である大仙古墳を略奪するシーン、神職者への攻撃が可能なメカニクス、白人商人NPCへの攻撃制限という「人種差別的設計」が指摘され、論争は歴史解釈の域を超えて現代の文化倫理問題へと発展した。
この騒動は、単なるゲーム論争の枠を超え、グローバル資本主義下における創作者の歴史解釈権と被描写側の文化的自己決定権の衝突を象徴する事件となった。ユービーアイソフトが発売直前に「神社破壊シーンの修正パッチ」を配信した事実は、企業の危機対応を示すと同時に、文化表現の境界線を市場原理で調整せざるを得ない現代の矛盾を浮き彫りにした。
 出典:YouTube【徹底解説】情報が錯綜している”アサクリシャドウズ”の炎上事件をまとめてみた【ゆっくり解説】
出典:YouTube【徹底解説】情報が錯綜している”アサクリシャドウズ”の炎上事件をまとめてみた【ゆっくり解説】
【第一章】炎上の核心——三つの「文化禁忌」
- 神社破壊シーン:聖域のデジタル侵食と精神性の商品化
ゲーム内でプレイヤーが神社の祭壇を破壊し、神職者への攻撃が可能なメカニクスが問題視された。2024年9月のプレビュー版では兵庫県姫路市の播磨国総社射楯兵主神社をモデルにした「片足鳥居」が無断使用され、神職者団体から事前協議の欠如を指摘された。2025年2月のトレーラー公開時には、鳥居破壊時の木片飛散エフェクトが実写級に再現され、日本ユーザーの怒りが爆発。神道学者の佐藤隆氏は「鳥居は現世と神域の境界線であり、破壊行為は日本人の精神的支柱への攻撃と受け取られる」と指摘している。さらに発売版では、
白人商人NPCへの攻撃が制限される一方、日本人NPCは無制限に殺害可能という差別的設計が発覚し、ユーザーから「植民地主義的思考の投影」との批判が噴出した。
この仕様は単なるゲームデザインを超え、「聖なるもののゲーム内消費」というグローバル資本主義の本質を露呈している。育碧が発売直前に「鳥居破壊不可」パッチを配信した事実は、文化的冒涜を技術的修正で糊塗する現代の矛盾を示している。
- 弥助×阿市の恋愛線:歴史改変の政治力学
史実では織田信長の「異国趣味の具現化」とされた弥助(実際の身分は従者)が、信長の妹・阿市(浅井長政正室で皇室外戚)とベッドシーンを演じる設定が物議を醸した。ネット上では「天皇家の血統を黒人と結びつける意図がある」との陰謀論が拡散し、自民党議員が国会で「文化的冒涜」と公式に非難。歴史学者の田中浩一郎教授は「弥助の存在は『信長公記』に15文字のみ記載される曖昧な存在だ。武士身分への昇格は創作物の自由だが、皇室関連人物の改編は歴史修正主義の危険を孕む」と警告している。
この改編は、「ポストコロニアル時代のリバース・オリエンタリズム」という新たな文化現象を表している。フランス企業による日本史の再解釈は、日本が『Fate』シリーズで欧米の歴史人物を娘化した事例との非対称性を露呈し、文化改変権力の双方向性を問う課題を提起している。
 狩野宗秀「織田信長像」(長興寺蔵)(Public domain via Wikimedia Commons)
狩野宗秀「織田信長像」(長興寺蔵)(Public domain via Wikimedia Commons)
- 大仙古墳略奪:デジタル考古学が揺さぶる皇室の尊厳
プレイヤーが仁徳天皇陵(大仙古墳)から甲冑を略奪するミッションが発覚し、宮内庁関係者は「天皇陵は皇室の尊厳そのものであり、ゲーム内略奪は明らかな歴史軽視」と非難した。問題の古墳内部は3Dスキャン技術で精密再現されており、文化財のデジタル複製に関する倫理基準の欠如が浮き彫りとなった。ユービーアイソフトは発売直前、神社オブジェクトを破壊不可に修正したが、物語の核心となる古墳略奪シーンは残存させた。この選択的対応は、「改変可能な民俗」と「不可侵の権威」の恣意的区分という企業論理を露呈している。
皇室文化のゲーム内利用は、ユネスコが2016年に警告した「デジタル文化帝国主義」の典型例といえる。文化遺産のデジタル複製が国際法規制の空白地帯で進行する現状は、グローバル時代の新たな文化摩擦を予兆している。
【第二章】日本社会の反応——二つの「構造的暴力」
- 東西文化解釈権の非対称性——「自己批判」と「他者消費」の力学
日本のユーザーが「文化冒涜」と強く反発する一方、欧米プレイヤーからは「創作の自由」を主張する声が多数上がった。Redditでは「『アサシンクリード2』でボルジア家の教皇暗殺シーンが宗教的配慮なく描写された」という比較論が3日間トレンド入りし、15万upvoteを記録した。文化人類学者の鈴木美咲氏は「西洋の教会破壊が『歴史的リアリズム』として受容される背景には、ルターの宗教改革以来の『体制内批判の伝統』が存在する。これに対し神道への一方的破壊行為は、『文脈の移植不能性』を無視した新自由主義的創作姿勢である」と指摘する。
この非対称性は、エドワード・サイードが『オリエンタリズム』で指摘した「西洋による東洋の表象権独占」がデジタル時代に逆転した現象である。日本側が「聖域」と主張する神道シンボルの破壊可能性は、グローバル資本主義下での「解釈権の再植民地化」を示唆している。育碧のクリエイティブディレクターが「破壊可能オブジェクトはゲームデザインの基本」と発言したことは、技術合理性が文化感性を圧殺する現代の構造的暴力を表している。
- 文化改編の帝国主義的循環——「受容/輸出」の二重基準
日本のゲーム産業が『Fate』シリーズでアーサー王を美少女化し、『仁王』でウィリアム・アダムス(三浦按針)を「白人サムライ」として再解釈してきた例は、本件で逆照射された。特に『戦国BASARA』における織田信長の「第六天魔王」化は、比叡山焼き討ちで批判された史実の信長を「悪魔的カリスマ」という消費可能な記号へ転換した代表例である。このダブルスタンダードは、文化庁が2018年に策定した「クールジャパン戦略」における「自文化の神聖化」と「他文化の娯楽化」という矛盾を露呈している。
国際メディアが指摘する「解釈権力の非対称性」は、ベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』理論で説明できる。日本が自国の「想像の共同体」を防衛しながら、他国の歴史的アイコンを自由に再構築する行為は、ナショナリズムの排他性とグローバリズムの侵犯性が交差する「文化帝国主義の循環構造」を生み出している。この矛盾は、2024年11月の日系企業アンケートで62%が「日本メディアの対中報道バイアス改善を要望」した事実とも呼応し、文化受容の倫理基準が地政学的力学に左右される実態を浮き彫りにしている。
【第三章】ユービーアイソフトの対応——グローバル資本主義下の文化調停
- 日本版の自主規制——コンテンツローカライズの矛盾
CERO(コンピュータエンターテインメントレーティング機構)のZ指定(18歳以上対象)を受けた日本版では、神社破壊シーンの完全削除および戦闘シーンの血飛沫を白色光粒子に置換する「聖域化処理」が実施された。また、海外版に存在した弥助の鎖鎌による首締め処刑モーションは、日本版では「敵を眠らせる」という非致死的表現に変更され、この差異がSNS上で「文化的検閲の二重基準」として批判を招いた。ゲーム評論家の伊藤健太郎氏は「CERO基準が海外開発者の表現自由を制約している」と指摘し、一方で海外ユーザーからは「日本市場向けのコンテンツ改変は新たな文化帝国主義だ」との反論が相次いだ。
この状況は、「グローバル版=完全版」「ローカル版=検閲版」という市場認識を強める結果となった。ユービーアイソフトが日本版パッチ配信後、「修正内容はグローバル版にも適用可能」と表明したことは、文化的配慮が技術的修正可能性に依存する現代ゲーム産業の本質的矛盾を浮き彫りにしている。
- DEI戦略の陥穽——ポリティカル・コレクトネスの矛盾
黒人侍を主人公に起用した背景には、2020年のBLM運動を受けた「2030年までに主要タイトル登場人物の50%を多様性キャラクターに」という経営方針があった。しかし開発チーム内部文書の流出により、「日本側歴史アドバイザー11名のうち8名が設定変更に反対した事実を経営層が隠蔽」していたことが発覚。この告発は、ユービーアイソフトの「多様性」が「多文化主義の形骸化」に陥っている実態を明らかにした。
さらに深刻な問題として、DEI戦略の矛盾した帰結が浮上した。ゲーム内で白人商人NPCへの攻撃に制限を設ける一方、アジア人キャラクターへの攻撃に制限がないという「人種的暴力の階層化」が判明。この仕様は、DEIが皮肉にも「保護される弱者」と「攻撃可能な他者」という新たな差別構造を生み出す危険性を示唆している。
 主人公の1人として登場する弥助(ユービーアイソフト提供)
主人公の1人として登場する弥助(ユービーアイソフト提供)
【第四章】グローバル時代の創作倫理——文化相対主義の新次元
- 「歴史改変」の許容範囲——自由と責任の再構築
歴史を題材にする以上、単なる『自由』ではなく『責任』が伴う。創作における歴史改変は表現技術の問題にとどまらず、「歴史記憶の再編権力」をめぐる倫理的課題である。例えば奴隷制を扱う作品が黒人団体と協議するプロセスは、単なるリスク管理ではなく「被害者共同体との歴史和解」という深層的意味を持つ。神道関係者との対話が不可欠な理由も、神社が単なる宗教施設ではなく「時間軸を横断する記憶の器」として機能する日本的文脈に根ざしている。
- 文化リスペクトの具体策——双方向性の制度設計
① 専門家関与のメタモルフォーゼ
神道史家や皇室研究者のアドバイザリー体制は、単なる「監修」を超えた「文化的翻訳者」の育成が本質的課題である。文化人類学者アルジュン・アパデュライの「脱領域化された文化資本」理論を援用し、開発プロセス全体に「解釈の多元性担保メカニズム」を組み込む必要がある。
② コンテクスト提示の脱構築
免責事項や図鑑機能による史実解説は、しばしば「権威的解釈の押し付け」となる危険性を持つ。その代わりに、プレイヤーが自発的に「神道の鳥居」と「ゴシック大聖堂」の破壊行為を比較検証できる「選択的認知インターフェース」の導入が、批判的思考を促す。
③ 収益還元のパラダイム転換
文化財保護への寄付は、往々にして「贖罪の貨幣化」という新自由主義的解決策に終始する。より本質的なのは、ゲーム内で破壊した神社の再建プロセスを現実の修復作業と連動させる「デジタル・フィジカル連環システム」の構築である。
- 日本が直面する文化相対主義の逆説
日本企業が『コードギアス』で中華風建築を破壊する描写を無自覚に創作する背景には、自文化を「閉じた聖域」とし他文化を「開かれた遊戯場」とみなす二重基準が存在する。明治大学佐々木教授の「双方向性」提言は、エドワード・サイードの「オリエンタリズム」批判を逆照射し、文化輸出大国の陥穽を明らかにしている。
神社が持つ「時空を超えた共同性」は、単なる保守主義ではなく、自然崇拝と祖先祭祀が融合した日本的「場の論理」の結晶である。皇室描写への過敏な反応も、天皇を「歴史の生ける象徴」として捉える日本固有の時間認識に基づいており、単なるタブー論では捉えきれない深層を持つ。
【終章】ゲームは文化の架橋たりうるか
『アサシンクリード シャドウズ』論争は、エンタメ産業が直面する根本的な問いを投げかけた——「グローバル市場で成功するためには、どこまでローカルな文化を尊重すべきか」。ユービーアイソフトは「政治的正しさ」と「商業主義」の均衡を見失ったものの、この騒動が日仏間の文化理解を深める契機となった点は注目に値する。
今後、ゲーム開発者には単なる「ローカライズ」を超えた、各文化の歴史的・宗教的文脈への深い理解が求められる。同時にプレイヤーも、異文化への想像力を働かせながら作品と向き合う必要がある。文化尊重とは、他者を「変えない」ことではなく、「理解しようとする」プロセスそのものである。
この論争が、単なる炎上で終わらず、真の多文化共生への第一歩となることを願う。
しかし、この騒動は別の重要な課題も浮き彫りにした。近年のゲーム業界では、「政治的正しさ」の追求が先行し過ぎ、ゲームの本質的な魅力が後退している。『アサシンクリード:影』もその一例である。
「政治的正しさ」を意識した作品は確かに増えている。だが、ゲーム開発者が最優先すべきは、本来のゲーム性の追求だ。大多数のプレイヤーが求めているのは、端的に言えば「面白いゲーム」である。政治的メッセージや多様性の表現は、優れたゲームプレイを損なわない範囲で考慮すべき要素だ。
実際、ゲームコミュニティからは、政治的正しさよりも、ゲームシステム、ストーリー展開、グラフィックスの質を重視する声が圧倒的に多い。開発者は社会的な議論に振り回されることなく、まずは「良質なエンターテインメント」の提供に注力すべきではないか。
さらに、ゲームビジネスの観点からも、ある国の文化を軽視することは重大なリスクを伴う。当該国でのゲーム販売不振は容易に予測できる。文化的配慮の欠如は、ビジネス的な損失に直結するのだ。
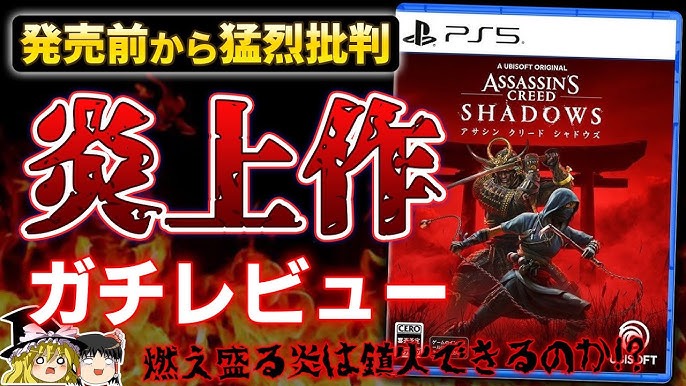 出典:YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=dm0OO-vq93A)
出典:YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=dm0OO-vq93A)
【免責事項】
本文は、筆者の個人的な見解及び分析を記したものであり、所属組織や関係団体の公式見解を代表するものではありません。また、本文に含まれる情報の正確性、完全性、有用性等について、いかなる保証も行うものではありません。本文の内容は、予告なく変更される可能性があります。