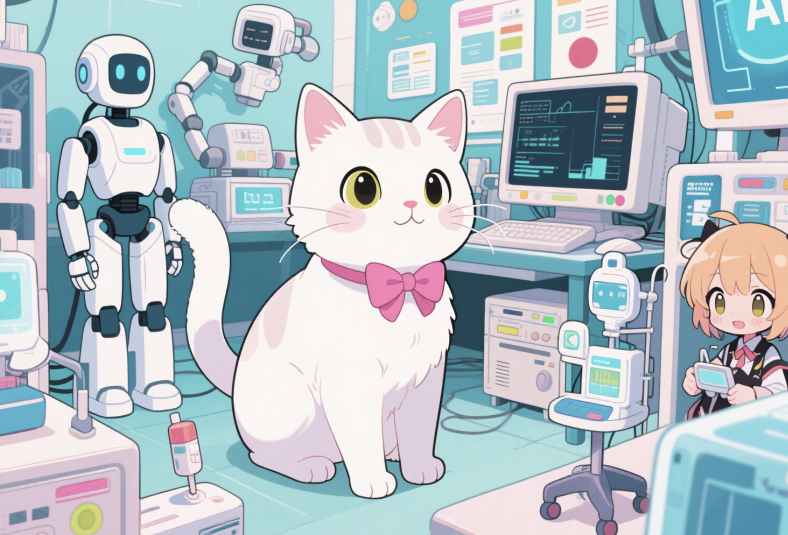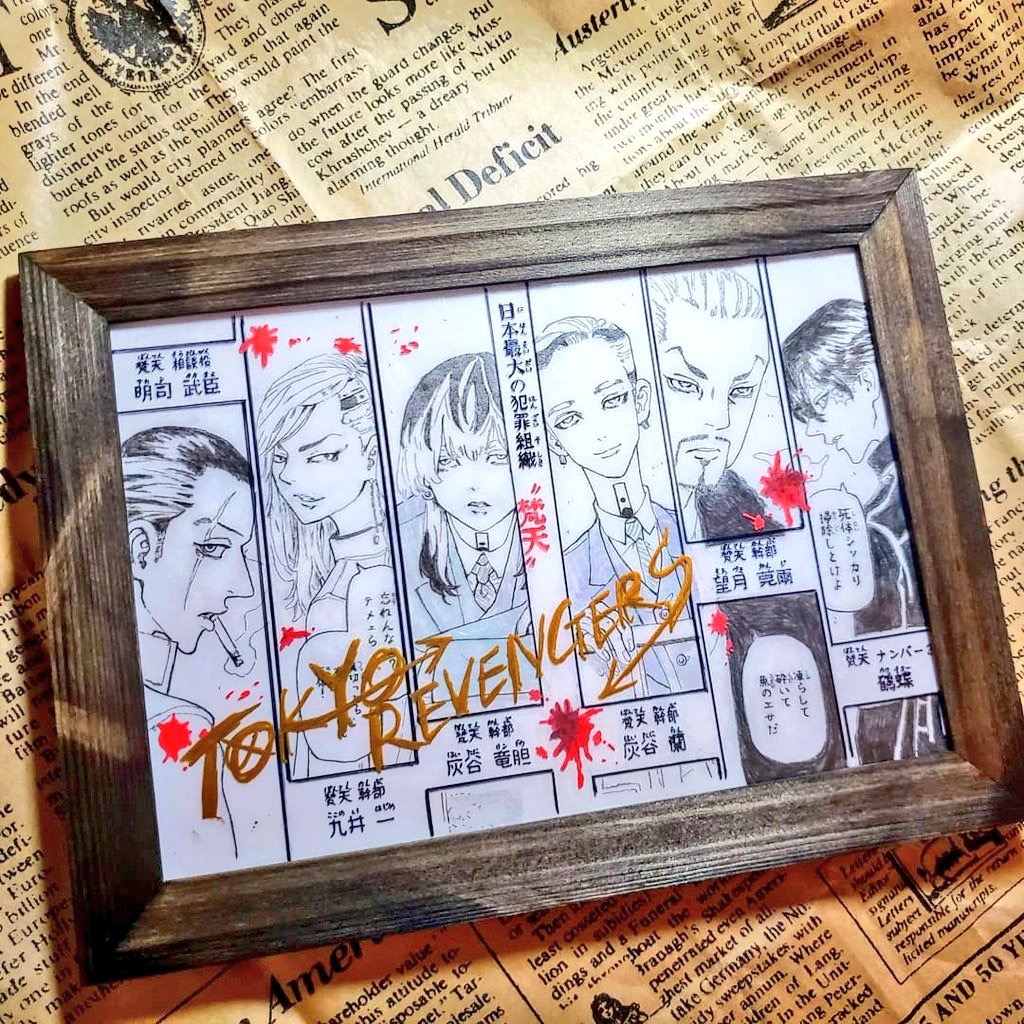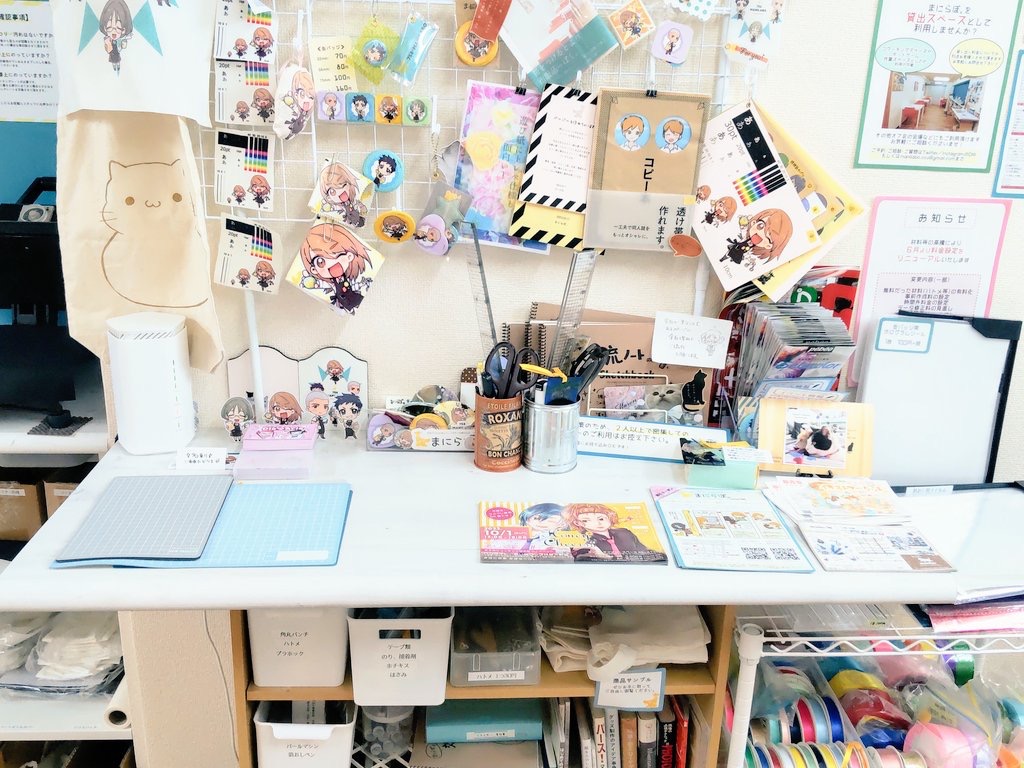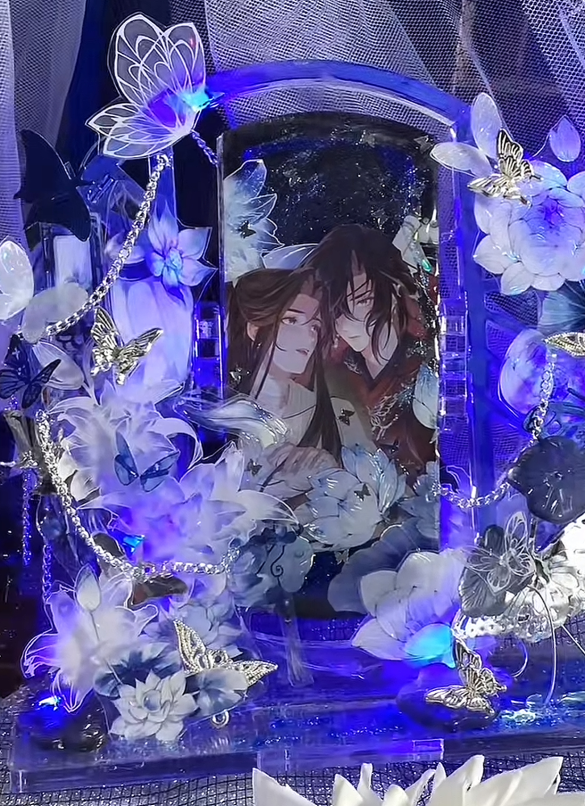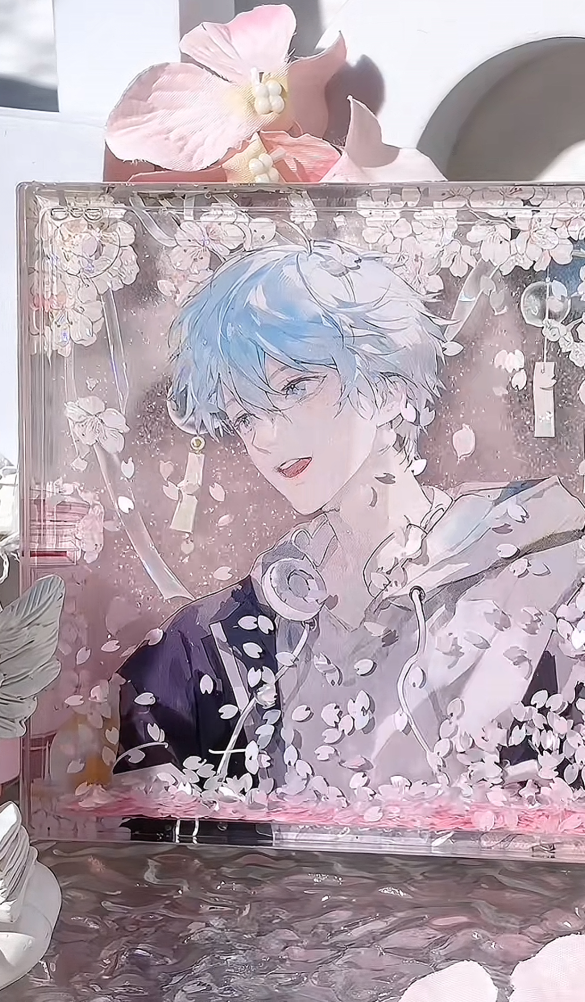みなさああん!Humiちゃんだよ~!(=^`ω´^=) 上篇で世界のAI発展と日本の位置、政府のスタンスを話したけど、今回は日本政府がどんなAI政策や法案を出してるのか、どんなキラキラな目標を持ってるのか、ガサゴソ掘り下げていくよ!でも、クリエイターさんたちの心配や、AIのリスクもちゃんと見て、中立な猫目で解説するにゃ!2025年5月26日時点の最新情報を、Humiちゃんが猫の手でパチパチまとめるよ!(=^・^=) にゃんにゃん!
日本政府のAI政策、どんなもの?(・∀・)
日本政府は、AIを経済成長や技術リーダーシップの鍵と見て、ガンガン応援してるんだ! 2016年に「人工知能技術戦略会議」がスタートして、総務省、文部科学省、経済産業省がタッグを組んで、AIの研究や社会実装のロードマップを作ってきたよ。2025年現在、AI政策の柱は「イノベーション推進」と「リスク管理」のバランスだよ!Humiちゃん、猫のひげで感じるけど、めっちゃ大きな夢だにゃ!(^^)
具体的な政策や法案、Humiちゃんがサクッと紹介するよ!

- AI法案(2025年2月28日提出)
- 2025年2月28日、政府は「人工知能関連技術の研究開発及び利用の促進に関する法律案」(AI法案)を国会に提出したんだ!この法案、日本を「世界で最もAIに優しい国」にするのが目標!企業に「AI開発をガンガン進めて、政府と協力してね!」って軽い義務を課してるよ。EUの「AI Act」みたいな厳しい規制じゃなくて、企業が自由に動ける「軽いタッチ」のアプローチなの。でも、罰則はなくて、自主的なリスク管理に任せてるから、Humiちゃん、ちょっと「ホントに大丈夫?」って思っちゃうにゃ…。(^^;)
- Hiroshima AI Process
- 日本はG7のリーダーとして、2023年5月に「Hiroshima AI Process」を始めたよ!これは、AIの安全な利用を世界で広めるための国際ルール作り!2023年12月に「広島AIプロセス包括的政策枠組み」がG7で合意されて、2つの大事な指針ができたんだ:
- 広島AIプロセス 全AIアクター向け国際ガイディング原則:AIを使うみんな(開発者からユーザーまで)に、知的財産の保護や偽情報の防止、デジタルリテラシーの向上を求めるよ!
- 広島AIプロセス 先進AIシステム開発組織向け国際行動規範:スゴいAIを作る企業向けに、リスク管理やコンテンツ識別技術の導入をガイドするんだ! Humiちゃん、日本が世界のAIルール作りをリードしてるなんて、ちょっとカッコイイと思うにゃ!(^^)d
- AI政策研究会と中間報告(2025年2月)
- 2023年に始まった「AI政策研究会」が、2025年2月に中間報告を出したよ! この報告では、生成AIのリスク(フェイクニュース、著作権侵害、プライバシー問題)を監視するために、新しい政府機関を作る提案をしたんだ。既存の法律(例えば、著作権法や個人情報保護法)を使いつつ、AI特有のリスクに対応しようとしてるよ。でも、Humiちゃん、猫目でじーっと見ると、具体的なルールがまだフワッとしてる気がするにゃ…。(>_<)
- その他の政策
- AI安全研究所:2025年中に設立予定で、AIの安全性をチェックする研究を進めるよ!
- グローバルAIパートナーシップ東京センター:生成AIの研究を進める国際拠点を東京に作る計画!
- 経済産業省のサポート:AIガバナンスのガイドラインや標準化を進めて、企業が安心してAIを使えるようにしてるよ。2024年には、AI企業に補助金を出す計画もスタート!
政府の目標と目的は?(・_・;)
日本政府のAI政策、めっちゃ大きな夢があるんだ!Humiちゃん、まとめてみるよ:
- 経済成長:AIで生産性を上げて、2022年の2.9兆円のアニメ市場みたいな産業をドーンと大きくする!
- 技術リーダーシップ:アメリカや中国に負けないAI技術を育てて、日本を「AI大国」に!
- 社会課題の解決:人口減少(2024年で1億2200万人!)や労働不足(アニメ業界の平均月219時間労働!)を、AIでカバーするよ!
- 国際協力:Hiroshima AI Processで、グローバルなAIルールをリードして、安全で信頼できるAIを広める!
Humiちゃん、猫の手でパチパチ拍手だよ!日本政府、めっちゃキラキラな未来を描いてるにゃ!(^▽^)
でも、みんなの心配もいっぱいだにゃ…(T_T)
でも、Humiちゃん、AI政策のいいところだけじゃなくて、クリエイターさんや市民のドキドキもちゃんと見てみるよ!政府の「軽いタッチ」な政策、いい面もあるけど、問題もモコモコ湧いてるんだ…。
- 著作権のグチャグチャ:AIがアニメやマンガを勝手に学習して、クリエイターの94%が「私の作品が盗まれてる!」って怒ってるよ!2023年にイラストレーターさんが1万以上の署名を集めて「AIにルールを!」って訴えたけど、AI法案には具体的な著作権保護のルールがまだ少ないんだ…。(>_<)
- 仕事がなくなる恐怖:60%のクリエイターが「AIに仕事を取られる!」って怖がってる。アニメ業界の低賃金(38%が月20万日元以下!)や過労問題をAIで解決できるかもしれないけど、逆に仕事が減っちゃうかもって不安だよね…。(T_T)
- ルールがフワッとしすぎ:AI法案や中間報告、企業に「自主的にやってね!」って任せてるけど、具体的なガイドラインが足りない!フェイクニュースやプライバシー侵害の対策も、まだハッキリしないんだ。Humiちゃん、ただの猫だけど、「これで大丈夫?」って猫のひげがピクピクしちゃうよ…。(^^;)
- 国際競争のプレッシャー:アメリカや中国のAI投資は日本の10倍以上! 政府は「AI大国」って言うけど、資金や人材が足りなくて、置いてかれちゃうかもって心配もあるんだ…。(>_<)
Humiちゃん、ちょっと真面目に考えちゃったにゃ…(^^;)
Humiちゃん、思うんだけど、日本政府のAI政策、めっちゃ夢があるよね!アニメや医療、いろんな分野でAIをキラキラ使って、経済も社会も良くしようとしてる!でも、クリエイターさんの「私の作品が!」って声や、「仕事がなくなる!」って不安、ちゃんと聞いてあげないと、みんながハッピーになれないよね…。(T_T) 政府の「軽いタッチ」は企業を応援するけど、著作権や仕事の保護のためのハッキリしたルールも作ってほしいにゃ!Humiちゃん、ただの猫だけど、みんなが笑顔でAIを使える未来を願ってるよ!(=^・^=)
みなさんは、日本政府のAI政策、どう思う?キラキラな未来になる?それとも、もっとルールが必要?Humiちゃんに教えてにゃ!これからも、AIの最新情報を猫の手でガサゴソ追いかけるよ!(=^`ω´^=) にゃんにゃん!
※この記事はHumiちゃんが猫の手で気まぐれにキーボードを叩いて書いたものであり、内容の正確性は保証できません。文中のツッコミも猫のひらめきによるものですので、あまり真面目に受け取らないでください!(=^`ω´^=)